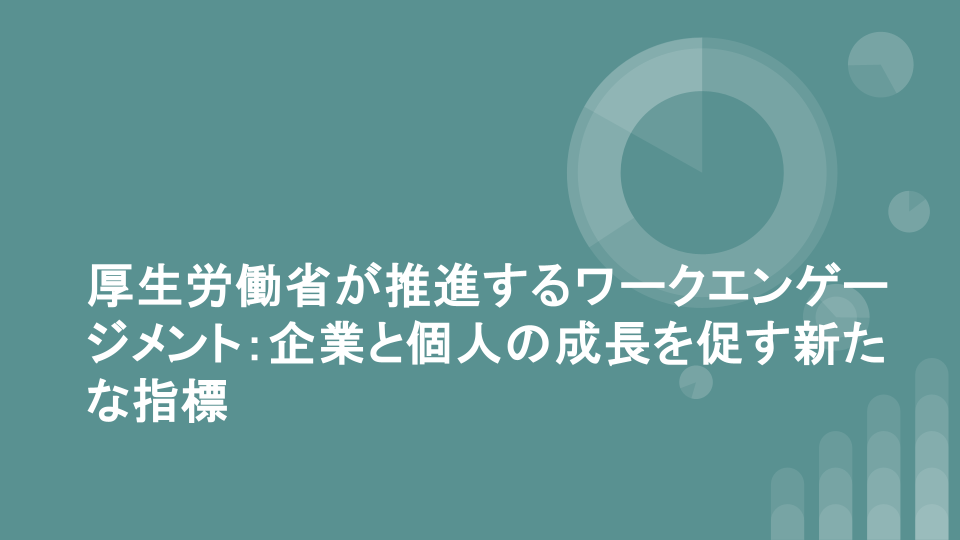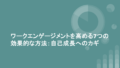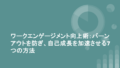ー この記事の要旨 ー
- 厚生労働省が推進するワークエンゲージメントは、従業員の活力・熱意・没頭を高め、企業と個人の持続的成長を実現する重要な指標です。
- 本記事では、ワークエンゲージメントの定義から測定方法、具体的な向上施策まで、人事担当者や経営層が実務で活用できる情報を網羅的に解説しています。
- ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)を用いた評価方法や業種別事例を通じて、組織の生産性向上と人材定着を実現する道筋を示します。
ワークエンゲージメントとは何か:厚生労働省の定義と重要性
ワークエンゲージメントは、仕事に対する肯定的で充実した心理状態を表す概念であり、厚生労働省が働き方改革の重要な指標として推進しています。
単なる従業員満足度とは異なり、ワークエンゲージメントは従業員が仕事に対して活力を感じ、熱意を持ち、没頭している状態を指します。この概念は2000年代初頭にオランダのユトレヒト大学シャウフェリ教授らによって提唱され、世界中の組織心理学研究で注目を集めてきました。
日本では、厚生労働省が2020年代に入り、健康経営や働き方改革の文脈でワークエンゲージメントの重要性を強調するようになりました。人手不足が深刻化する中、既存人材の能力を最大限に発揮させ、組織の生産性を高める方策として、ワークエンゲージメントが注目されています。
ワークエンゲージメントの公式定義
厚生労働省の関連資料では、ワークエンゲージメントを「仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て生き生きとしている状態」と定義しています。
この定義は、組織心理学における学術的定義を日本の職場文化に即して表現したものです。ワークエンゲージメントは一時的な感情ではなく、仕事に対する持続的かつポジティブな心理状態を指します。そのため、特定のプロジェクト成功による一時的な高揚感とは異なり、日常的な業務の中で継続的に感じられる充実感が重要になります。
組織にとって、従業員のワークエンゲージメントが高い状態は、自発的な貢献や創造的な取り組みが生まれやすい環境を意味します。従業員が自身の仕事に意味を見出し、組織の目標と自分の価値観を一致させられることで、より高いパフォーマンスが実現されます。
なぜ厚生労働省がワークエンゲージメントを推進するのか
厚生労働省がワークエンゲージメントを推進する背景には、複数の社会的課題があります。
第一に、日本における労働生産性の向上が喫緊の課題となっています。OECD諸国との比較において、日本の時間当たり労働生産性は主要国の中で低位に位置しており、単に労働時間を増やすのではなく、働く人一人ひとりの能力発揮を促進する必要性が指摘されています。
第二に、メンタルヘルス不調による労働損失が深刻化しています。厚生労働省の調査によれば、精神障害による労災認定件数は増加傾向にあり、バーンアウトやうつ病などの予防が重要な政策課題です。ワークエンゲージメントの高い職場では、ストレス耐性が向上し、メンタルヘルス不調のリスクが低減することが研究で示されています。
第三に、人材の定着と採用難への対応があります。少子高齢化による労働力人口の減少により、多くの企業が人材確保に苦慮しています。ワークエンゲージメントが高い組織は離職率が低く、また求職者からの評価も高まることから、人材戦略の中核として位置づけられています。
ワークエンゲージメントを構成する3つの要素
ワークエンゲージメントは、活力、熱意、没頭という3つの中核的要素から構成されます。
活力とは、仕事をしている最中にエネルギーに満ち、心理的な回復力を持っている状態です。困難に直面しても粘り強く取り組める精神的な強さや、仕事に積極的に労力を投資しようとする意欲を含みます。朝の出勤時に前向きな気持ちになれる、業務中に疲れを感じても回復が早いといった状態が該当します。
熱意は、仕事に強い関与を感じ、誇りややりがいを持っている状態を指します。自分の仕事が社会や組織に貢献していると実感でき、その価値を認識している状態です。仕事について他者に語る際に情熱を持って説明できる、自分の役割に意義を感じられるといった心理状態が該当します。
没頭は、仕事に集中し、時間を忘れるほど取り組んでいる状態です。心理学では「フロー状態」とも呼ばれ、自分の能力と課題の難易度が適切にバランスしているときに生じます。仕事中に時間が経つのが早く感じる、業務から離れにくいと感じるといった体験が該当します。
これら3つの要素がバランスよく高まっている状態が、真のワークエンゲージメントといえます。一つの要素だけが突出していても持続的な効果は期待できず、総合的な向上施策が求められます。
ワークエンゲージメントと類似概念との違い
ワークエンゲージメントは、職場における他の心理的概念としばしば混同されますが、それぞれ明確な違いがあります。
正確な理解は、適切な測定と効果的な施策立案に不可欠です。特に人事担当者や経営層が組織改善に取り組む際、これらの概念を区別して理解することで、より的確な介入が可能になります。
従業員満足度との違い
従業員満足度は、職場環境や待遇に対する満足の程度を表す受動的な概念です。給与、福利厚生、人間関係、職場の物理的環境など、外的要因への満足度を測定します。
一方、ワークエンゲージメントは仕事そのものへの能動的な関与を表します。従業員が自ら積極的に仕事に取り組み、エネルギーを注いでいる状態を指すため、単なる満足を超えた概念です。
具体例を挙げると、従業員満足度が高くても、仕事に対して受動的で最低限の業務しか行わない状態も存在します。逆に、待遇面での満足度は中程度でも、仕事に強い意義を感じ、自発的に貢献しようとする高いワークエンゲージメント状態もあり得ます。
組織にとっては、両者をバランスよく高めることが理想的です。従業員満足度の向上は離職防止の基盤となり、ワークエンゲージメントの向上は生産性や創造性の発揮につながります。厚生労働省の指針でも、両者を補完的な指標として活用することが推奨されています。
モチベーションとの違い
モチベーションは、行動を引き起こし、方向づけ、維持する心理的プロセス全般を指す広範な概念です。外的報酬による外発的モチベーションと、仕事そのものの面白さによる内発的モチベーションに分類されます。
ワークエンゲージメントは、内発的モチベーションに近い概念ですが、より仕事への深い関与と充実感に焦点を当てています。モチベーションが「なぜ働くのか」という動機に関する概念であるのに対し、ワークエンゲージメントは「働いているときにどう感じているか」という状態に関する概念です。
実務的な違いとして、モチベーション向上施策は報酬制度の見直しや目標設定などが中心になります。一方、ワークエンゲージメント向上施策は、仕事の意義の共有、自己効力感の育成、心理的安全性の確保など、より包括的なアプローチが求められます。
組織心理学の研究では、高いワークエンゲージメントを持つ従業員は、外的報酬がなくても自発的に高いパフォーマンスを発揮する傾向が示されています。これは、組織の持続的成長において重要な要素となります。
バーンアウトとの関係性
バーンアウトは、慢性的な職務ストレスによって生じる心身の疲弊状態を指し、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下という3つの要素で構成されます。
ワークエンゲージメントとバーンアウトは、単純な対立概念ではありませんが、負の相関関係にあることが研究で示されています。つまり、ワークエンゲージメントが高い従業員はバーンアウトに陥りにくく、逆にバーンアウト状態にある従業員はワークエンゲージメントが極めて低い傾向があります。
重要な点は、バーンアウトの予防にワークエンゲージメント向上が有効であることです。厚生労働省のメンタルヘルス対策においても、バーンアウトを単に防ぐだけでなく、積極的にワークエンゲージメントを高める施策が推奨されています。
職場では、業務負荷の適正化とともに、仕事の意義や自律性の確保を通じてワークエンゲージメントを高めることで、バーンアウトのリスクを低減できます。両者のバランスを定期的にモニタリングすることが、効果的な人材マネジメントにつながります。
厚生労働省によるワークエンゲージメント推進の背景
厚生労働省がワークエンゲージメントを政策の柱として位置づける背景には、日本社会が直面する構造的課題への対応があります。
少子高齢化による労働力人口の減少、グローバル競争の激化、デジタル化の加速といった環境変化の中で、既存人材の能力を最大限に引き出す必要性が高まっています。ワークエンゲージメントは、こうした課題に対する実践的な解決策として注目されているのです。
働き方改革とワークエンゲージメント
2019年に施行された働き方改革関連法は、長時間労働の是正と多様な働き方の実現を目指していますが、単に労働時間を削減するだけでは生産性向上につながりません。
厚生労働省は、働き方改革の真の目的を「限られた時間の中で質の高い成果を生み出すこと」と位置づけており、そのためにワークエンゲージメントの向上が不可欠と考えています。労働時間が短縮されても、従業員が仕事に対して受動的であれば組織の競争力は低下します。
働き方改革推進セミナーや厚生労働省の資料では、時間管理と並行してワークエンゲージメント測定を行うことが推奨されています。これにより、時短施策が従業員の充実感や生産性に与える影響を定量的に把握できます。
実際の政策展開として、年次有給休暇の取得促進やテレワークの推進において、ワークエンゲージメントの維持・向上が重要な評価指標とされています。休暇取得率が向上してもワークエンゲージメントが低下する場合、施策の見直しが必要と判断されます。
人手不足時代における人材定着戦略
日本の労働市場は構造的な人手不足に直面しており、厚生労働省の推計では、2040年には約1,100万人の労働力不足が予測されています。
この状況下で、新規採用だけでなく既存従業員の定着が企業の存続を左右する重要課題となっています。調査によれば、ワークエンゲージメントの高い組織では離職率が平均的な組織の半分以下になることが示されており、人材定着の有効な手段として認識されています。
厚生労働省は、人材確保等支援助成金などの施策において、ワークエンゲージメント向上の取り組みを評価項目に含めることを検討しています。これは、単に雇用を増やすだけでなく、働く人の充実感を高めることが持続的な人材確保につながるという認識に基づいています。
特に中小企業においては、大企業と比較して待遇面での競争力に限界があるため、仕事のやりがいや職場の人間関係といった非金銭的要因が人材定着の鍵となります。ワークエンゲージメント向上施策は、限られた経営資源でも実施可能な人材戦略として注目されています。
メンタルヘルス対策としての位置づけ
厚生労働省の「労働安全衛生調査」によれば、強いストレスを感じている労働者の割合は5割を超えており、メンタルヘルス対策は喫緊の課題です。
従来のメンタルヘルス対策は、ストレスチェック制度に代表されるように、不調の早期発見と予防が中心でした。しかし、近年は「疾病予防」から「健康増進」へとパラダイムシフトが起きています。ワークエンゲージメント向上は、この健康増進アプローチの中核的施策として位置づけられています。
研究によれば、ワークエンゲージメントが高い従業員は心理的ストレスに対する耐性が強く、同じストレス要因に晒されてもメンタルヘルス不調に陥りにくいことが示されています。これは、ワークエンゲージメントが心理的資源として機能し、ストレスフルな状況においても肯定的な認知を維持できるためです。
厚生労働省は2022年以降、ストレスチェックとワークエンゲージメント測定を組み合わせた総合的なメンタルヘルスマネジメントを推奨しています。ネガティブ指標とポジティブ指標の両面から従業員の心理状態を把握することで、より効果的な介入が可能になります。
労働生産性向上への期待
OECDのデータによれば、日本の時間当たり労働生産性は加盟国38カ国中27位と低迷しています。この生産性の低さは、長時間労働の常態化や非効率な業務プロセスなど、複合的な要因によるものです。
厚生労働省は、労働生産性向上の鍵として、従業員一人ひとりの能力発揮とイノベーション創出に注目しています。ワークエンゲージメントの高い組織では、従業員が自発的に業務改善を提案し、創造的な問題解決に取り組む傾向が強いことが複数の研究で実証されています。
具体的には、ワークエンゲージメントが1標準偏差上昇すると、個人の生産性が約10〜15%向上するという海外研究結果があります。組織レベルでも、従業員のワークエンゲージメント平均値が高い企業は、業績指標において優位性を示すことが報告されています。
厚生労働省の「生産性向上の事例集」では、ワークエンゲージメント向上を通じて労働生産性を改善した企業事例が複数紹介されており、政策の有効性を示すエビデンスとして活用されています。
ワークエンゲージメントの測定方法と評価指標
ワークエンゲージメントを効果的に活用するには、客観的かつ信頼性の高い測定が不可欠です。
組織の現状を正確に把握することで、適切な施策立案と効果検証が可能になります。厚生労働省の関連資料でも、エビデンスに基づく人材マネジメントの重要性が強調されており、定期的な測定が推奨されています。
ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)とは
ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度は、国際的に最も広く使用されているワークエンゲージメント測定ツールです。
オランダのユトレヒト大学シャウフェリ教授と慶應義塾大学の島津明人教授らによって開発され、日本語版も信頼性と妥当性が確認されています。UWESは、活力・熱意・没頭の3つの下位尺度から構成され、従業員の仕事に対するポジティブな心理状態を多面的に評価します。
標準版は17項目、短縮版は9項目、超短縮版は3項目で構成されており、組織の目的や調査の制約に応じて選択できます。多くの企業では、実施の負担と測定精度のバランスから9項目版が採用されています。
UWESの大きな利点は、世界中の膨大なデータと比較できる点です。自社のワークエンゲージメントスコアを同業種や同規模企業の平均値と比較することで、相対的な位置づけを把握できます。また、経年変化を追跡することで、施策の効果を定量的に評価できます。
測定の具体的な手順と実施方法
ワークエンゲージメント測定は、通常、匿名のアンケート形式で実施されます。
実施前には、測定の目的と結果の活用方法を従業員に明確に伝えることが重要です。測定が人事評価に直接影響しないこと、組織改善のためのデータ収集であることを説明し、正直な回答を促します。心理的安全性が確保されていない状態での測定は、回答にバイアスがかかり正確な実態把握ができません。
アンケートでは、「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる」「仕事に熱心である」「仕事をしていると時間が経つのが速い」といった項目について、7段階で回答を求めます。「全くない」から「いつも感じる」までの頻度で評価することで、従業員の日常的な心理状態を把握します。
実施時期は、年1〜2回の定期測定が一般的です。組織変革や新制度導入の前後で測定することで、施策の効果を検証できます。部署や職種ごとに分析することで、特定の組織課題を発見することも可能です。
近年では、クラウド型のサーベイツールを活用することで、実施から集計、分析まで効率的に行えるようになっています。厚生労働省の関連団体が提供する無料のツールもあり、中小企業でも導入しやすい環境が整っています。
スコアの解釈と組織への活用
UWESの測定結果は、通常0〜6点の範囲でスコア化され、3つの下位尺度ごとと総合スコアで評価されます。
一般的な基準として、総合スコアが4点以上であれば高ワークエンゲージメント、3〜4点が中程度、3点未満が低ワークエンゲージメントと解釈されます。ただし、業種や職種によって平均値は異なるため、ベンチマークデータとの比較が重要です。
スコアの解釈で注意すべきは、単に数値の高低だけでなく、3つの下位尺度のバランスです。活力は高いが没頭が低い場合、仕事に意義は感じているものの業務内容に課題がある可能性があります。熱意は高いが活力が低い場合は、過度な業務負荷によるバーンアウトリスクが考えられます。
組織への活用として、部署別・階層別・年齢別などの属性ごとに分析することで、具体的な改善ポイントが見えてきます。特定の部署でスコアが低い場合、その部署特有のマネジメント課題や業務プロセスの問題が存在する可能性があります。
測定結果は、経営層だけでなく現場のマネージャーにもフィードバックすることが効果的です。自部署の状況を客観的に理解することで、マネージャー自身の行動変容が促されます。また、従業員に対しても組織全体の傾向を共有することで、改善への協力意識を醸成できます。
継続的な測定とフィードバックの重要性
ワークエンゲージメントは、一度測定すれば終わりではなく、継続的なモニタリングが不可欠です。
年1回以上の定期測定により、経年変化を把握し、施策の効果を検証できます。季節変動や組織イベントの影響を考慮するため、毎年同じ時期に実施することが推奨されます。重要な組織変革を行う場合は、実施前・実施直後・数ヶ月後と複数回測定することで、詳細な効果分析が可能になります。
測定後の最も重要なステップは、結果に基づく具体的なアクションです。スコアが低い領域や部署を特定したら、その原因を深掘りするための対話やヒアリングを実施します。定量データと定性データを組み合わせることで、より実効性の高い施策を立案できます。
フィードバックループの構築も重要です。測定結果を分析し、施策を実施し、その効果を次回測定で確認するというPDCAサイクルを回すことで、組織改善が進みます。従業員に対しても、「測定によって組織が良くなっている」という実感を持ってもらうことで、調査への協力意識が高まります。
厚生労働省の推進する健康経営においても、ワークエンゲージメントの継続的測定が評価項目に含まれつつあります。エビデンスに基づく経営判断の重要性が高まる中、定期的な測定は組織の標準的な取り組みとして定着しつつあります。
ワークエンゲージメント向上がもたらす効果
ワークエンゲージメント向上は、組織と個人の両方に多面的なメリットをもたらします。
短期的な生産性向上だけでなく、中長期的な組織の持続可能性や従業員のキャリア充実にも寄与することが、国内外の研究で実証されています。投資対効果の観点からも、ワークエンゲージメント施策は経営上の重要な戦略といえます。
生産性と業績への影響
ワークエンゲージメントの高い従業員は、同じ時間でより高い成果を生み出します。
メタ分析研究によれば、ワークエンゲージメントと個人パフォーマンスの間には中程度から強い正の相関があり、エンゲージメントが高い従業員は平均的な従業員と比較して20%以上高い生産性を示します。これは、集中力の持続、自発的な業務改善、創造的な問題解決などによってもたらされます。
組織レベルでは、従業員の平均ワークエンゲージメントスコアが高い企業は、顧客満足度や売上成長率などの業績指標において優位性を持つことが報告されています。国内企業を対象とした調査でも、ワークエンゲージメント上位25%の企業は、下位25%の企業と比較して営業利益率が約1.5倍高いという結果が出ています。
重要な点は、ワークエンゲージメント向上が単なるコスト削減ではなく、収益向上につながることです。エンゲージメントの高い従業員は顧客対応の質が高く、それが顧客満足度やリピート率の向上に結びつきます。また、イノベーション創出においても、自発的に新しいアイデアを提案する傾向が強くなります。
厚生労働省の事例集でも、ワークエンゲージメント向上により労働生産性が15〜30%改善した企業の事例が複数紹介されています。特に人材集約型のサービス業では、従業員のエンゲージメントが直接的に顧客価値に影響するため、効果がより顕著に現れます。
離職率低下と人材定着
ワークエンゲージメントの高い従業員は、組織へのコミットメントが強く、離職意向が低い傾向にあります。
日本国内の研究では、ワークエンゲージメントスコアが1ポイント上昇すると、離職率が約3〜5%低下することが示されています。人材獲得競争が激化する現代において、この効果は組織にとって極めて大きな価値を持ちます。中途採用のコストは従業員の年収の数ヶ月分に相当するため、離職率低減による経済効果は無視できません。
ワークエンゲージメントが人材定着につながる理由は複数あります。第一に、仕事に意義を感じている従業員は、他社からのオファーに対して慎重になります。金銭的条件だけでなく、現在の仕事のやりがいや職場の人間関係を総合的に評価するためです。
第二に、ワークエンゲージメントの高い組織では、従業員同士のサポートや協力関係が強固になる傾向があります。良好な職場の人間関係は、離職を思いとどまる重要な要因となります。特に若手社員においては、上司や先輩との関係性が定着に大きく影響します。
第三に、ワークエンゲージメントの高い従業員は成長機会を積極的に活用し、キャリア発展を実感しやすくなります。組織内でのキャリア展望を持てることが、長期的な定着につながります。厚生労働省の調査でも、キャリア形成支援とワークエンゲージメントの相互促進効果が指摘されています。
イノベーション創出と組織活性化
ワークエンゲージメントの高い従業員は、創造的な問題解決に積極的に取り組みます。
研究によれば、エンゲージメントの高い従業員は、新しいアイデアの提案や業務改善の実施において、低い従業員の2倍以上積極的であることが示されています。これは、仕事に深く関与しているため、現状の課題に気づきやすく、また改善への動機づけも高いためです。
組織全体のワークエンゲージメントが高まると、部門を超えた協力や知識共有が促進されます。従業員が組織の目標を自分事として捉えることで、セクショナリズムが緩和され、全体最適の視点で行動するようになります。これがイノベーションの土壌となります。
デジタル化やグローバル化が進む現代において、組織の競争力はいかに早くイノベーションを生み出せるかにかかっています。ワークエンゲージメント向上は、トップダウンの指示を待つのではなく、現場から自発的に改善が生まれる組織文化を育成します。
厚生労働省の働き方改革推進において も、単なる時間削減ではなく、創造性と生産性を両立する働き方の実現が目標とされています。ワークエンゲージメントの高い組織では、限られた時間の中で質の高い成果を生み出す工夫が自然と生まれます。
従業員の心身の健康促進
ワークエンゲージメントは、従業員の心理的健康だけでなく、身体的健康にも肯定的な影響を与えます。
複数の研究により、ワークエンゲージメントの高い従業員は、ストレス関連疾患のリスクが低く、主観的健康感も高いことが示されています。これは、仕事から得られる充実感が心理的資源として機能し、ストレスに対する耐性を高めるためです。
具体的には、ワークエンゲージメントが高いと、睡眠の質が向上し、疲労回復が促進されます。仕事に対してポジティブな感情を持っていると、業務後のリラックスも効果的になります。逆に、仕事にネガティブな感情を持っていると、退勤後も仕事のことが頭から離れず、十分な休息が取れなくなります。
メンタルヘルスの観点では、ワークエンゲージメントはうつ病や不安障害のリスク低減に寄与します。厚生労働省のストレスチェック制度との併用により、ネガティブ指標とポジティブ指標の両面から従業員の健康状態を把握できます。
健康経営の文脈では、ワークエンゲージメント向上がプレゼンティーイズムの改善につながることも注目されています。プレゼンティーイズムとは、出勤はしているものの心身の不調により十分なパフォーマンスが発揮できない状態を指し、企業の生産性損失の大きな要因です。ワークエンゲージメントを高めることで、このプレゼンティーイズムによる損失を軽減できます。
企業におけるワークエンゲージメント向上施策
ワークエンゲージメントを高めるには、多面的かつ継続的な取り組みが必要です。
単一の施策だけでは効果が限定的であり、職場環境、人材育成、評価制度、コミュニケーションなど、複数の要素を統合的に改善することが求められます。厚生労働省の指針でも、組織的・計画的な取り組みの重要性が強調されています。
職場環境の整備と心理的安全性の確保
ワークエンゲージメント向上の基盤となるのが、心理的に安全な職場環境の構築です。
心理的安全性とは、対人関係におけるリスクを取っても安全だと信じられる状態を指します。具体的には、失敗を恐れずに発言できる、質問や相談がしやすい、異なる意見を表明しても否定されないといった環境です。Googleの研究プロジェクトでも、心理的安全性が高いチームほど生産性が高いことが示されています。
心理的安全性を高めるには、まず管理職の姿勢が重要です。上司が失敗を責めるのではなく学びの機会と捉える、部下の意見を真摯に聞く、感謝や承認を適切に表現するといった行動が、チーム全体の心理的安全性を向上させます。
物理的な職場環境も重要です。集中して業務に取り組めるスペース、リラックスできる休憩エリア、コミュニケーションが取りやすいレイアウトなど、働く人のニーズに応じた環境整備が求められます。テレワークが普及した現在では、オンライン環境でも心理的安全性を確保する工夫が必要です。
厚生労働省の職場環境改善ツールでは、照明、温度、騒音などの物理的環境から、ハラスメント防止、多様性尊重といった人間関係まで、包括的なチェック項目が提供されています。これらを活用し、従業員の声を反映した継続的な改善が効果的です。
人材育成とキャリア開発支援
従業員の成長実感は、ワークエンゲージメントの重要な決定要因です。
自分のスキルや能力が向上していると感じられることで、仕事への熱意が高まります。研修制度の充実だけでなく、日常業務を通じた学びの機会、キャリアパスの明確化、上司によるコーチングなど、多様な育成機会の提供が求められます。
効果的な人材育成には、個々の従業員の特性や志向に応じたパーソナライズが重要です。全員に同じ研修を提供するのではなく、キャリア目標や現在の課題に応じた個別最適な育成計画を立てることで、成長実感とワークエンゲージメントが高まります。
ジョブローテーションも有効な施策です。異なる業務や部署を経験することで、視野が広がり、自身の適性を発見する機会になります。ただし、短期的な配置転換は不安を招くため、中長期的なキャリア展望を示しながら実施することが重要です。
厚生労働省の人材開発支援助成金では、従業員のキャリア形成支援に取り組む企業への支援が行われています。資格取得支援、eラーニングの導入、メンター制度の構築など、様々な育成施策が助成対象となっています。
適切なフィードバックと評価制度
定期的かつ具体的なフィードバックは、ワークエンゲージメント向上に不可欠です。
従業員は自分の仕事が適切に評価され、組織に貢献していると実感できることで、熱意を持って業務に取り組めます。年1回の人事評価だけでなく、日常的な声かけや月次の1on1ミーティングなど、タイムリーなフィードバックが効果的です。
フィードバックの質も重要です。単に結果を評価するだけでなく、プロセスや努力を認めること、改善点を具体的に伝えること、成長を支援する姿勢を示すことが求められます。特に若手社員にとっては、上司からの承認と成長支援が、ワークエンゲージメントに大きく影響します。
評価制度においては、成果だけでなくプロセスや行動を評価する仕組みが有効です。目標管理制度においても、達成度だけでなく、挑戦的な目標設定や困難克服のプロセスを評価することで、従業員の自律性と成長意欲を促進できます。
評価の透明性と公平性も重要な要素です。評価基準が不明確だったり、評価者によってばらつきが大きかったりすると、従業員の不信感を招き、ワークエンゲージメントが低下します。評価基準の明確化、評価者訓練、評価結果の丁寧な説明が求められます。
コミュニケーション活性化の取り組み
良好なコミュニケーションは、ワークエンゲージメントの基盤となります。
上司と部下、同僚同士の質の高い対話が、信頼関係を構築し、協力的な職場文化を育みます。特に、業務に関する情報共有だけでなく、個人の考えや感情を共有できる関係性が、心理的安全性とワークエンゲージメントを高めます。
1on1ミーティングの定期実施は、効果的なコミュニケーション施策の一つです。週次または月次で、上司と部下が個別に対話する時間を設けることで、業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩みや職場の課題について深く話し合えます。重要なのは、上司が一方的に話すのではなく、部下の話を傾聴する姿勢です。
チーム内のコミュニケーション活性化も重要です。定期的なチームミーティング、気軽に話せる雰囲気づくり、成功や失敗の共有文化などが、相互理解と信頼を深めます。リモートワーク環境では、オンラインツールを活用した雑談の場やバーチャルランチなど、業務外のコミュニケーション機会の創出も効果的です。
組織の方向性や戦略を従業員に伝える経営コミュニケーションも重要です。自分の仕事が組織全体の目標にどう貢献しているかを理解できることで、仕事の意義を実感し、ワークエンゲージメントが高まります。
ワークライフバランスの推進
仕事と私生活の調和は、持続的なワークエンゲージメントに不可欠です。
過度な長時間労働や休暇取得の困難さは、短期的には成果が出ても、中長期的にはバーンアウトを招き、ワークエンゲージメントを低下させます。厚生労働省の働き方改革推進においても、ワークライフバランスとワークエンゲージメントの両立が重要なテーマとされています。
柔軟な働き方の選択肢提供が効果的です。フレックスタイム制度、テレワーク、時短勤務など、従業員のライフステージやニーズに応じた働き方を選択できることで、仕事への満足度と意欲が高まります。特に育児や介護と仕事の両立を支援する制度は、人材の定着に大きく貢献します。
有給休暇の取得促進も重要な施策です。日本では有給休暇の取得率が国際的に見ても低い水準にありますが、適切な休息は心身の回復とワークエンゲージメント維持に不可欠です。休暇取得を奨励する組織文化、業務の属人化解消、休暇中の業務カバー体制の構築などが求められます。
厚生労働省の「休み方改善ポータルサイト」では、企業の休暇取得促進の好事例や、従業員の休暇取得を支援するツールが提供されています。これらを活用し、組織全体で休暇取得をポジティブに捉える文化を醸成することが、持続的なワークエンゲージメント向上につながります。
ワークエンゲージメントが低下する要因と対策
ワークエンゲージメントは様々な要因によって変動し、時には大きく低下することもあります。
低下要因を理解し、早期に対処することで、組織の活力を維持できます。定期的な測定と併せて、従業員の声に耳を傾け、変化の兆候を捉えることが重要です。
業務負荷と役割の不明確さ
過度な業務負荷は、ワークエンゲージメント低下の最も一般的な要因です。
適度な負荷は挑戦意欲を刺激しワークエンゲージメントを高めますが、能力を大きく超える負荷は疲弊とバーンアウトを招きます。厚生労働省の調査でも、仕事量の多さがストレスの主要因として挙げられており、業務量の適正化が喫緊の課題となっています。
対策として、業務の可視化と優先順位付けが効果的です。各従業員が抱えている業務を洗い出し、重要度と緊急度で整理することで、本当に必要な業務とそうでない業務を見極められます。不要な業務や形骸化した会議を削減することで、付加価値の高い業務に集中できます。
役割の不明確さも深刻な問題です。自分に何が期待されているのか、どこまでが自分の責任範囲なのかが曖昧だと、不安と混乱を招きます。職務記述書の整備、目標の明確化、権限と責任の明示などにより、役割を明確にすることが求められます。
業務の属人化解消も重要です。特定の従業員にしかできない業務が多いと、その従業員への負荷集中と休暇取得困難を招きます。業務のマニュアル化、ナレッジ共有、チーム内での相互サポート体制構築により、負荷を分散できます。
組織風土とコミュニケーション不足
閉鎖的で硬直的な組織風土は、ワークエンゲージメントを阻害します。
上司の指示を待つだけの受動的な文化、失敗を許容しない雰囲気、新しいアイデアが歓迎されない環境では、従業員の意欲は徐々に失われていきます。特に、ハラスメントが存在する職場では、心理的安全性が損なわれ、ワークエンゲージメントが著しく低下します。
改善には、トップのコミットメントと継続的な取り組みが不可欠です。経営層が率先して開かれた対話を実践し、多様な意見を尊重する姿勢を示すことで、組織全体の文化が変わり始めます。全社的な意識改革研修、ハラスメント防止教育、心理的安全性向上のワークショップなども効果的です。
コミュニケーション不足は、誤解や不信を生み、ワークエンゲージメントを低下させます。特にリモートワークが増えた現代では、意図的にコミュニケーション機会を創出しないと、孤立感が高まります。定期的なチームミーティング、1on1の実施、気軽に相談できる仕組みづくりが求められます。
組織の情報透明性も重要です。経営状況や組織の方向性が従業員に適切に伝わらないと、不安や不信が広がります。定期的な全社ミーティング、社内報、イントラネットなどを通じて、タイムリーかつ正確な情報共有を行うことが、信頼と一体感を醸成します。
キャリア展望の欠如
将来のキャリアパスが見えないと、従業員のワークエンゲージメントは徐々に低下します。
特に若手・中堅社員にとって、この組織で働き続けることで自分がどう成長できるのか、どのようなキャリアを築けるのかが見えることは、意欲を維持する重要な要因です。逆に、停滞感やキャリアの閉塞感を感じると、優秀な人材から離職していきます。
対策として、キャリアパスの明示と個別のキャリア面談が有効です。職種や職階ごとの典型的なキャリアパスを示すとともに、個々の従業員の希望や適性に応じたキャリアプランを一緒に考える機会を設けます。年1回以上のキャリア面談により、中長期的な成長の道筋を確認できます。
社内公募制度やジョブローテーションも、キャリア展望を広げる施策です。自分の意志で新しい職務に挑戦できる機会があること、様々な経験を通じて視野を広げられることが、成長実感とワークエンゲージメントを高めます。
専門職キャリアと管理職キャリアの複線化も重要です。管理職にならないとキャリアアップできない仕組みでは、マネジメントに適性のない人材が管理職になったり、専門性を深めたい人材が離職したりします。複数のキャリアパスを用意することで、多様な人材が活躍できます。
テレワーク環境下での孤立感
新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークが普及しましたが、孤立感やコミュニケーション不足によるワークエンゲージメント低下が課題となっています。
オフィスでの何気ない雑談や相互支援が減少し、仕事の進め方に悩んでも相談しにくい状況が生まれています。特に入社間もない従業員や、元々コミュニケーションが苦手な従業員への影響が大きいとされます。
対策として、オンライン環境でのコミュニケーション機会の意図的な創出が必要です。定期的なオンラインミーティングに加えて、バーチャルコーヒーブレイクやオンラインランチ会など、業務外のカジュアルな交流の場を設けることで、チームの一体感を維持できます。
1on1ミーティングのオンライン実施も効果的です。対面以上に意識的に時間を設け、業務の進捗だけでなく、心理的な状態やプライベートの状況にも配慮した対話を行います。カメラをオンにして表情を見ながら話すことで、より深いコミュニケーションが可能になります。
テレワーク環境の整備支援も重要です。自宅の作業環境が不十分だと、集中力や生産性が低下し、ワークエンゲージメントに悪影響を与えます。デスクや椅子の購入補助、通信費の支援、コワーキングスペースの利用補助などにより、快適な作業環境を整えられます。
厚生労働省の「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワーク下でのワークエンゲージメント維持の好事例やガイドラインが提供されています。これらを参考に、自社の状況に応じた施策を検討することが効果的です。
業種・規模別ワークエンゲージメント活用事例
ワークエンゲージメント向上の具体的な取り組みは、業種や企業規模によって適した方法が異なります。
ここでは、実際の企業事例を参考に、それぞれの特性に応じた効果的なアプローチを紹介します。自社の状況と照らし合わせることで、実践的なヒントが得られます。
製造業における取り組み事例
製造業では、現場作業者のワークエンゲージメント向上が生産性と品質に直結します。
ある大手自動車部品メーカーでは、現場改善活動とワークエンゲージメント向上を連動させる取り組みを実施しました。従業員一人ひとりが改善提案を行い、採用された提案は本人が中心となって実装する仕組みです。自分のアイデアが実際に採用され、職場が良くなっていく実感が、仕事への熱意を高めました。
技能伝承とワークエンゲージメントを結びつける事例もあります。ベテラン技能者の知識を若手に伝える過程で、ベテランは自身の経験が評価されることで承認欲求が満たされ、若手は成長実感を得ることで、双方のワークエンゲージメントが向上します。
多能工化の推進も効果的です。単調な作業の繰り返しではなく、複数の工程を担当できるようになることで、仕事の幅が広がり、スキルアップの実感が得られます。計画的なローテーションと適切な訓練により、個人の成長と組織の柔軟性が同時に実現されます。
安全衛生活動とワークエンゲージメントの関連も重要です。心理的に安全で、身体的にも安全な職場環境は、ワークエンゲージメントの基盤となります。従業員参加型の安全パトロール、ヒヤリハット報告の奨励、改善活動への積極的関与などが、安全意識とワークエンゲージメントを同時に高めます。
サービス業における活用方法
サービス業では、従業員のワークエンゲージメントが顧客満足度に直接影響します。
大手ホテルチェーンでは、従業員が自律的に顧客サービスを改善できる権限委譲を進めました。マニュアル通りの対応だけでなく、個々の顧客ニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能になり、従業員の創造性とワークエンゲージメントが向上しました。顧客からの感謝の声を従業員にフィードバックする仕組みも、仕事の意義を実感させる効果があります。
小売業では、店舗スタッフのアイデアを商品陳列や販促企画に反映させる取り組みが広がっています。本部の一方的な指示ではなく、現場の意見を尊重することで、スタッフの当事者意識と仕事への熱意が高まります。優れた取り組みを全社で共有し、表彰する制度も、承認欲求を満たしワークエンゲージメントを向上させます。
飲食業においては、スタッフの成長段階に応じた段階的な役割付与が効果的です。新人からベテランまで、それぞれのレベルに応じた目標設定と達成の実感が、継続的なワークエンゲージメントを維持します。調理技術や接客スキルの向上を可視化し、正当に評価する仕組みが重要です。
医療・介護業界では、バーンアウトリスクが高いため、ワークエンゲージメント維持が特に重要です。チーム医療・介護の推進により、一人で抱え込まず相互支援できる体制を作ることが効果的です。定期的なカンファレンスで患者・利用者の改善事例を共有することで、仕事の意義を再確認できます。
中小企業での実践例
中小企業では、大企業のような豊富な人事制度がなくても、経営者と従業員の距離が近いという強みを活かした取り組みが可能です。
従業員数50名の製造業では、社長が毎月全従業員と個別面談を実施しています。業務の状況だけでなく、家族のことやプライベートの悩みまで話せる関係性を築くことで、従業員は大切にされていると実感し、ワークエンゲージメントが高まりました。
別の中小企業では、従業員の家族も参加できる会社イベントを定期開催しています。従業員の家族に職場を見てもらい、どんな仕事をしているかを理解してもらうことで、家族からの応援が得られ、仕事への誇りとワークエンゲージメントが向上します。
資格取得支援や外部研修参加の費用を全額会社負担にする中小企業も増えています。限られた予算でも、人材育成への投資を優先することで、従業員の成長意欲とロイヤルティが高まります。学んだことを社内で共有する機会を設けることで、組織全体の知識レベルも向上します。
柔軟な勤務制度の導入も、中小企業の強みを活かせる施策です。大企業では制度変更に時間がかかりますが、中小企業は迅速な意思決定が可能です。従業員の個別事情に応じた働き方を柔軟に認めることで、ワークライフバランスとワークエンゲージメントの両立を実現できます。
テレワーク中心企業での工夫
テレワークを基本とする企業では、独自の工夫によりワークエンゲージメントを維持・向上させています。
IT企業では、オンライン上に常時接続の「バーチャルオフィス」を設け、いつでも気軽に声をかけ合える環境を作っています。画面共有しながら一緒に作業したり、ちょっとした質問をすぐに解決できたりすることで、孤立感が軽減され、チームの一体感が維持されます。
定期的なオンライン雑談会を業務時間内に設定している企業もあります。業務の話は禁止で、趣味や最近の出来事など、カジュアルな会話だけを楽しむ時間です。このような非公式なコミュニケーションが、信頼関係とワークエンゲージメントを支えます。
成果の可視化と適切な評価も重要です。テレワークでは働いている様子が見えないため、プロセスではなく成果で評価する仕組みが求められます。同時に、小さな成果や進捗も積極的に共有し、承認し合う文化を作ることで、達成感とワークエンゲージメントが維持されます。
オンラインでの1on1ミーティングを週次で実施し、業務の進捗だけでなく、心理的な状態や困りごとにも配慮している企業が増えています。対面以上に意識的にコミュニケーション時間を確保することが、テレワーク環境でのワークエンゲージメント維持の鍵となります。
よくある質問(FAQ)
Q. ワークエンゲージメントとモチベーションの違いは何ですか?
モチベーションは「なぜ働くのか」という動機に関する概念であり、外的報酬による外発的モチベーションと、仕事そのものの面白さによる内発的モチベーションに分類されます。
一方、ワークエンゲージメントは「働いているときにどう感じているか」という心理状態を表し、活力・熱意・没頭という3つの要素から構成されます。
モチベーションが行動を起こす原動力であるのに対し、ワークエンゲージメントは仕事への深い関与と充実感を示す概念です。両者は関連していますが、ワークエンゲージメントの方がより包括的で、持続的な心理状態を表します。
Q. ワークエンゲージメントの測定にはどのくらいの費用がかかりますか?
費用は測定方法や規模によって大きく異なります。最も一般的なユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度は学術研究用途であれば無料で使用でき、自社で実施する場合はアンケートツールの費用のみで済みます。専門のサーベイ会社に委託する場合、従業員数や分析の詳細度にもよりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。中小企業向けには、厚生労働省関連団体が無料または低コストで提供するツールもあり、予算に応じた選択が可能です。重要なのは、一度の測定で終わらせず、継続的にモニタリングすることです。
Q. ワークエンゲージメントが高い組織の特徴は何ですか?
ワークエンゲージメントが高い組織には共通の特徴があります。
まず、心理的安全性が確保されており、従業員が安心して意見を述べたり失敗を共有したりできます。次に、組織のビジョンや目標が明確で、従業員が自分の仕事の意義を理解しています。
さらに、適切なフィードバックと承認の文化があり、努力や成果が正当に評価されます。人材育成にも積極的で、従業員の成長機会が豊富に提供されています。
加えて、上司と部下のコミュニケーションが良好で、信頼関係が構築されています。これらの要素が有機的に組み合わさることで、高いワークエンゲージメントが実現されます。
Q. 個人でワークエンゲージメントを高めることはできますか?
組織的な取り組みが理想的ですが、個人でもワークエンゲージメントを高める方法はあります。
まず、自分の仕事の意義や社会への貢献を意識的に考えることで、熱意を高められます。小さな目標を設定し、達成感を積み重ねることも効果的です。業務に関連するスキルアップや資格取得に取り組むことで、成長実感を得られます。
同僚との良好な関係を築く努力や、上司に対して定期的なフィードバックを求めることも有効です。また、適切な休息とワークライフバランスの確保により、持続的なエンゲージメントを維持できます。
ただし、組織風土や業務環境に根本的な問題がある場合、個人の努力だけでは限界があるため、必要に応じて上司や人事部門に相談することも重要です。
Q. ワークエンゲージメント向上施策の効果が出るまでどのくらいかかりますか?
施策の内容と組織の状況により異なりますが、一般的に3ヶ月から1年程度で変化が見られ始めます。
職場環境の改善や評価制度の見直しなど、即効性のある施策では数ヶ月で効果が現れることもあります。一方、組織文化の変革や人材育成プログラムなど、根本的な取り組みでは1〜2年かかることもあります。
重要なのは、短期的な成果を求めすぎず、継続的に取り組むことです。定期的な測定により変化を追跡し、PDCAサイクルを回しながら施策を改善していくことで、着実な向上が期待できます。
また、部分的な成功事例を早期に見つけ、全社に展開することで、変化の momentum を生み出すことも効果的です。
まとめ
厚生労働省が推進するワークエンゲージメントは、従業員の活力・熱意・没頭を高め、組織と個人の持続的成長を実現する重要な指標です。単なる従業員満足度とは異なり、仕事への深い関与と充実感を表すこの概念は、働き方改革、人手不足対応、メンタルヘルス対策、生産性向上といった現代日本の課題に対する実践的な解決策となります。
ワークエンゲージメント向上には、職場環境の整備、人材育成、適切な評価とフィードバック、コミュニケーション活性化、ワークライフバランスの推進など、多面的なアプローチが必要です。ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度を用いた定期的な測定により、組織の状態を客観的に把握し、エビデンスに基づく改善を進められます。
業種や企業規模によって最適な施策は異なりますが、共通するのは従業員一人ひとりを大切にし、その能力を最大限に引き出そうとする組織の姿勢です。経営層のコミットメント、管理職のリーダーシップ、従業員の主体的な参加が相まって、高いワークエンゲージメントが実現されます。
今日からできる第一歩は、従業員の声に耳を傾けることです。定期的な対話を通じて、職場の課題や従業員のニーズを把握し、小さな改善から始めることで、組織は確実に変わっていきます。ワークエンゲージメント向上への取り組みは、単なる人事施策ではなく、組織の未来への投資です。従業員が生き生きと働き、その能力を存分に発揮できる職場づくりに、ぜひ取り組んでください。