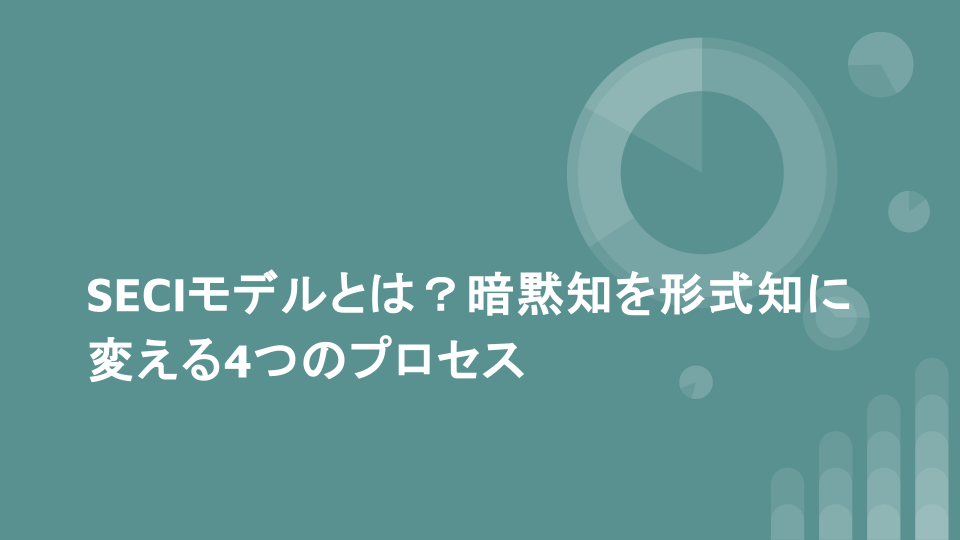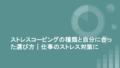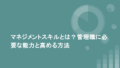ー この記事の要旨 ー
- SECIモデルとは、暗黙知と形式知の変換を通じて組織の知識を創造・拡大するフレームワークで、共同化・表出化・連結化・内面化の4プロセスで構成されています。
- 本記事では各プロセスの具体的な内容と職場での実践方法、うまく回らない原因と対策までを体系的に解説します。
- ベテランのノウハウを組織全体で活かし、属人化解消やイノベーション創出につなげる具体的なアプローチがわかります。
SECIモデルとは
SECIモデルとは、暗黙知と形式知の相互変換を通じて組織内で新たな知識を創造するプロセスを体系化したフレームワークです。一橋大学の野中郁次郎教授と竹内弘高教授が提唱し、ナレッジマネジメントの理論的基盤として世界的に知られています。
本記事ではSECIモデルの4つのプロセスと職場での実践方法に焦点を当てます。ナレッジマネジメントの全体像については関連記事「ナレッジマネジメントとは? 」で解説しています。
知識創造理論の基本的な考え方
SECIモデルの根底にあるのは「知識は個人の頭の中だけでなく、人と人との相互作用を通じて生まれ、広がる」という考え方です。
ベテラン営業担当者が持つ商談のコツ、熟練エンジニアが身につけた設計の勘所。こうした知識は、本人も言葉にしにくいものです。しかし、適切なプロセスを経れば、チームや組織全体で共有できる形に変換できます。SECIモデルは、その変換の道筋を4つの段階で示したものです。
ここがポイントです。SECIモデルは単なる情報共有の手法ではありません。既存の知識を組み合わせて「新しい知識を生み出す」創造のプロセスを説明している点が特徴です。
暗黙知と形式知の違い
SECIモデルを理解するには、暗黙知と形式知の区別を押さえておく必要があります。
暗黙知とは、言葉や文章で表現しにくい、経験や勘に基づく知識です。自転車に乗るコツ、顧客との信頼関係を築く呼吸、トラブル発生時の判断基準などがこれにあたります。「体で覚えた」「感覚でわかる」という類の知識で、本人も説明を求められると困ってしまうケースが多いものです。
形式知とは、マニュアル、手順書、データベースなど、言語や数式、図表で明確に表現された知識です。誰が読んでも同じ内容を理解でき、そのまま他者に伝達できます。
実は、組織内の価値ある知識の多くは暗黙知として個人の中に眠っています。SECIモデルは、この暗黙知を形式知に変換し、さらに新たな暗黙知として定着させる循環を設計するためのフレームワークです。
SECIモデルの4つのプロセス
SECIモデルは、共同化(Socialization)、表出化(Externalization)、連結化(Combination)、内面化(Internalization)の4段階で構成されています。それぞれの頭文字をとってSECIと呼ばれます。
共同化(Socialization)
体験の共有を通じて、言葉にならないノウハウを移転する。それが共同化のプロセスです。暗黙知から暗黙知への変換にあたります。
先輩社員の商談に同席して交渉の間合いを学ぶ、熟練技術者の作業を隣で見ながらコツを体得する。言葉で説明されなくても、一緒に過ごす中で「なんとなくわかってくる」経験は誰しもあるのではないでしょうか。これが共同化です。
具体的な場面としては、OJTでの同行営業、製造現場での師弟関係、プロジェクトチームでの協働作業などが該当します。注目すべきは、共同化では言語化されない微細なニュアンスまで伝わる点です。声のトーン、表情の変化、タイミングの取り方といった非言語情報も含めて知識が移転します。
表出化(Externalization)
表出化は、暗黙知を形式知に変換するプロセスで、言語化・文書化を通じて知識を可視化します。
「なぜうまくいったのか」を振り返り、成功要因を言葉にする。熟練者の判断基準をフローチャートに落とし込む。顧客対応のコツを事例集としてまとめる。こうした取り組みが表出化にあたります。
正直なところ、4つのプロセスの中で最も難しいのがこの表出化です。暗黙知は本人も意識していないことが多く、「どうやっているの?」と聞かれても「なんとなく」としか答えられないケースが少なくありません。比喩やたとえ話、具体的なエピソードを引き出す質問が、表出化を促す鍵になります。
連結化(Combination)
営業部門のベストプラクティスと開発部門の技術資料を統合して、新しい提案テンプレートを作る。複数プロジェクトの失敗事例を分析してリスクチェックリストを作成する。こうした知識の再構成が連結化です。形式知同士を組み合わせて新たな形式知を生み出すプロセスにあたります。
データベースへの情報蓄積、マニュアルの体系化、ナレッジベースの構築なども連結化の一環といえます。大切なのは、単に情報を集めるだけでなく、整理・分類・統合を通じて「使える形」に再編することです。
内面化(Internalization)
内面化は、形式知を暗黙知として自分のものにするプロセスで、学んだ知識を実践を通じて体得します。
マニュアルを読んで手順を理解し、実際にやってみて「こういうことか」と腑に落ちる。研修で学んだフレームワークを日常業務で使い続けるうちに、自然と使いこなせるようになる。これが内面化です。
見落としがちですが、内面化は単に「覚える」こととは異なります。知識を自分なりに咀嚼し、応用できる状態にまで高めるプロセスです。実践、反復、振り返りを通じて、形式知が「体に染み込んだ」暗黙知へと変わっていきます。
知識創造スパイラルの仕組み
SECIモデルの真価は、4つのプロセスが一度で終わらず、スパイラル状に繰り返されることで組織の知識が拡大・深化していく点にあります。
4つのプロセスが循環する理由
共同化で得た暗黙知は、表出化によって形式知に変換され、連結化で他の知識と組み合わさり、内面化で再び暗黙知として定着します。この内面化された暗黙知が、次の共同化の起点となって新たなサイクルが始まります。
たとえば、新人が先輩から商談のコツを学ぶ(共同化)。そのコツを「初回訪問チェックリスト」として文書化する(表出化)。他のメンバーの成功事例と統合して「商談マニュアル」に発展させる(連結化)。マニュアルを参考に実践を重ね、自分なりのスタイルを確立する(内面化)。この新たなスタイルが、また別の後輩に共有される。
ここがポイントです。このサイクルが回るたびに、知識は単に「伝わる」だけでなく「進化」していきます。元の知識に新たな視点や工夫が加わり、より洗練されたものになっていくのです。
組織レベルでの知識拡大
知識創造スパイラルは、個人から始まり、チーム、部門、組織全体へと拡大していきます。
個人レベルでは、1人の熟練者が持つノウハウが対象です。チームレベルでは、チーム内での共有と改良が進みます。部門レベルでは、複数チームの知見が統合されます。組織レベルでは、部門を超えた知識の連結が起こり、企業全体の競争力につながります。
野中教授は、このプロセスを支える「場」の重要性を強調しています。場とは、知識創造が起こる物理的・仮想的・精神的な空間のことです。会議室での対話、オンラインでの情報共有、心理的に安全なチームの雰囲気。こうした「場」が整っていなければ、スパイラルは回りません。
SECIモデルを職場で実践する方法
SECIモデルを理論として理解するだけでなく、日常業務に組み込むことで初めて効果が現れます。各プロセスを促進する具体的な方法を見ていきます。
※以下の事例はSECIモデルの活用イメージを示すための想定シナリオです。
IT企業B社の開発チームでは、ベテランエンジニアの退職を機に技術ノウハウの散逸が課題となりました。そこで、週1回30分の「技術共有タイム」を設け、ベテランが若手とペアで障害対応を行う機会を作りました(共同化)。対応後に「なぜその判断をしたか」を振り返り、判断フローをドキュメント化(表出化)。複数の事例を集約してトラブルシューティングガイドを作成し(連結化)、新人研修のカリキュラムに組み込みました(内面化)。3か月後、新人の障害対応時間が平均40%短縮されました。
共同化を促す「場」の設計
共同化には、体験を共有する機会と空間が必要です。
ペア作業やシャドーイング(業務同行)は共同化の基本形です。営業であれば同行営業、開発であればペアプログラミング、製造現場であれば師弟制度などが該当します。1on1ミーティングも、上司の思考プロセスを部下が学ぶ共同化の場として機能します。
実務では、「忙しくて教える時間がない」という声が出がちです。しかし、週に30分でもペア作業の時間を確保することで、言葉にならないノウハウが伝わります。「一緒にやる」機会を意図的に設計することが共同化の出発点です。
表出化を進める言語化の技術
表出化のカギは、暗黙知を引き出す「問い」の設計にあります。
「なぜそうしたのか」「他の選択肢はなかったか」「初心者がつまずきやすいポイントはどこか」。こうした問いを投げかけることで、本人も意識していなかった判断基準が言語化されます。
テンプレートの活用も有効です。成功事例であれば「状況・課題・行動・結果・学び」の5項目で整理する、失敗事例であれば「何が起きたか・原因・対策・教訓」の4項目で記録する、といった形式を用意しておくと、言語化のハードルが下がります。
週次の振り返りミーティングで「今週の気づき」を1人1分で共有するルールを設けている組織もあります。小さな習慣が、表出化の文化を育てます。
連結化と内面化を加速させる仕組み
連結化には、知識を蓄積・検索・更新できるシステムが欠かせません。
社内Wiki、ナレッジベース、FAQシステムなどが代表的なツールです。ツール選びで大切なのは、検索性と更新のしやすさです。登録されたナレッジが見つからない、更新が面倒で情報が古くなる、という状態では連結化は進みません。
内面化を促すには、学んだ知識を実践する機会を設けることが有効です。研修後に「学んだことを1週間以内に1回実践し、結果を報告する」というルールを設ける。ナレッジベースを読んだ後に「試してみた結果」を追記する仕組みを作る。こうした「知識を使う」機会を組み込むことで、形式知が暗黙知として定着していきます。
SECIモデルがうまく回らない原因と対策
SECIモデルを導入しても、期待どおりに機能しない組織は少なくありません。つまずきやすいポイントと対処法を整理します。
表出化が進まない組織の特徴
SECIモデルがうまく回らない最大の原因は、表出化のプロセスが滞ることです。
「言語化する時間がない」「どう書けばいいかわからない」「書いても誰も見ない」。こうした声が上がる組織では、表出化が進みません。暗黙知は暗黙知のまま個人に留まり、共同化と内面化だけが繰り返される状態になります。
対策としては、言語化の負荷を下げる工夫が必要です。テンプレートの用意、音声入力の活用、インタビュー形式での聞き取りなど、「書く」以外の方法も検討してみてください。また、「ナレッジ投稿は業務」と位置づけ、時間を確保することも欠かせません。
知識共有を阻む心理的障壁への対処法
「自分のノウハウを教えると、自分の価値がなくなる」という心理的障壁も、SECIモデルの阻害要因です。
この障壁を乗り越えるには、知識共有が評価される仕組みづくりがポイントです。ナレッジ投稿数や活用実績を人事評価に組み込む、共有したナレッジが役立った際にフィードバックが届く仕組みを作る、といった施策が考えられます。
経営層や管理職が率先して自分のノウハウを公開する姿勢も影響を与えます。「上司も惜しみなく教えてくれる」という空気があれば、メンバーも共有しやすくなります。心理的安全性(チーム内で自分の意見を安心して発言できる状態)の確保が、SECIモデルを回す土台といえるでしょう。
SECIモデル活用のメリット
SECIモデルを組織に根づかせることで得られるメリットは、属人化の解消、人材育成の効率化、イノベーション創出の3点に集約されます。
属人化の解消と業務標準化
SECIモデルの表出化・連結化が進めば、特定の担当者だけが知っているノウハウが可視化され、組織の共有財産になります。
「あの人がいないと回らない」という状態は、異動や退職で大きなリスクを招きます。SECIモデルを通じて暗黙知が形式知に変換されれば、誰でも一定水準の業務遂行が可能になります。引き継ぎの負荷軽減、業務品質の安定化といった効果が期待できます。
営業部門であれば、トップセールスの商談ノウハウが共有されることで、チーム全体の受注率向上につながるケースもあります。
人材育成の効率化
新人が一人前になるまでの期間を短縮できる点も大きなメリットです。
従来は「先輩の背中を見て覚える」しかなかった知識が言語化されていれば、新人は自分のペースで学習を進められます。OJTだけに頼る場合、教える側の力量や余裕によって育成スピードにばらつきが出がちです。SECIモデルで知識が形式知化されていれば、教育の質を一定水準に保てます。
開発部門であれば、障害対応手順のドキュメント化により、新人エンジニアが自力で問題解決できる範囲が広がります。企画部門であれば、過去の提案事例集が新人の企画力向上を後押しします。
イノベーション創出の土台
SECIモデルの連結化プロセスは、異なる知識の組み合わせから新しいアイデアが生まれる土台を作ります。
営業現場の顧客の声と、開発部門の技術情報が結びつけば、新製品のヒントが見つかるかもしれません。製造現場の改善ノウハウとバックオフィスの業務効率化事例が統合されれば、全社的な生産性向上につながる可能性があります。
組織学習の観点からも、SECIモデルは欠かせません。個人が学んだことを組織全体で共有・活用できる仕組みがあれば、組織としての学習能力が高まり、変化への適応力が強化されます。
よくある質問(FAQ)
SECIモデルの共同化と表出化の違いは?
共同化は体験共有、表出化は言語化のプロセスです。
共同化では言葉を介さず「一緒にやることで伝わる」知識が対象となります。先輩の仕事ぶりを見て学ぶ、同行営業でコツを体得する、といった場面が該当します。一方、表出化では「なぜそうするのか」「どう判断しているのか」を言葉や図表で説明し、文書として残します。
共同化は「感覚的な伝達」、表出化は「論理的な可視化」と捉えるとわかりやすいでしょう。
暗黙知を形式知に変換するコツは?
暗黙知の言語化は、具体的な質問を通じて「当たり前」を掘り起こすことがコツです。
「なぜその順番で作業するのか」「初心者がつまずきやすいポイントは」「成功したときと失敗したときの違いは何か」。こうした問いを投げかけることで、本人も意識していなかった判断基準が浮かび上がります。
テンプレートの活用も効果を発揮します。「状況・行動・結果・学び」の4項目で記録するフォーマットを用意すれば、言語化のハードルが下がります。
SECIモデルとナレッジマネジメントの関係は?
SECIモデルは、ナレッジマネジメントを実践する際の理論的基盤として位置づけられます。
ナレッジマネジメントが「組織の知識をどう活用するか」という全体像を示すのに対し、SECIモデルは「知識がどのように創造・変換されるか」のメカニズムを説明します。SECIモデルの4プロセスを意識することで、ナレッジマネジメントの施策をより効果的に設計できます。
どちらか一方ではなく、両者を組み合わせて活用することが実務では有効です。
SECIモデルを一人で実践できる?
個人レベルでも表出化・連結化・内面化の3プロセスは応用できます。
自分の経験を振り返って言語化する(表出化)、書籍やネットの情報と自分の知識を組み合わせる(連結化)、学んだことを実践して身につける(内面化)。こうした活動は一人でも取り組めます。
ただし、共同化のプロセスは他者との関わりが前提となるため、チームや組織で実践するほうがSECIモデル本来の効果を発揮できます。
SECIモデルの効果が出るまでの期間は?
効果が現れる期間は組織規模や取り組みの深さで異なります。
小さなチームで特定の業務に絞って実践する場合、1〜3か月で変化が見え始めるケースがあります。全社的な取り組みとして定着させるには、6か月〜1年以上の継続が必要になることも珍しくありません。
最初から大きな成果を求めず、小さな成功体験を積み重ねることが継続のポイントです。
リモートワーク環境でもSECIモデルは使える?
リモートワーク環境でもSECIモデルは活用できますが、共同化のプロセスに工夫が必要です。
対面での「一緒に作業しながら学ぶ」機会が減るため、オンラインでのペアワーク、画面共有を使った作業の可視化、動画による作業手順の記録といった代替手段を検討します。
表出化・連結化・内面化は、むしろデジタルツールとの相性が良い領域です。ナレッジベースやWikiの活用、非同期でのドキュメント共有など、リモート環境ならではの強みを活かせます。
まとめ
SECIモデルで成果を出すには、B社の事例が示すように、共同化の「場」を意図的に設け、表出化で言語化の習慣を作り、連結化・内面化の仕組みを業務に組み込むという流れがポイントです。
初めの1週間は、自部門で「言葉にされていないノウハウ」を3つ洗い出すことから始めてみてください。1か月後には、そのうち1つをテンプレートに沿って文書化し、チームで共有することを目標にします。
小さな表出化の積み重ねが、知識創造スパイラルを回す原動力となり、属人化の解消やナレッジマネジメントの実践にもつながっていきます。