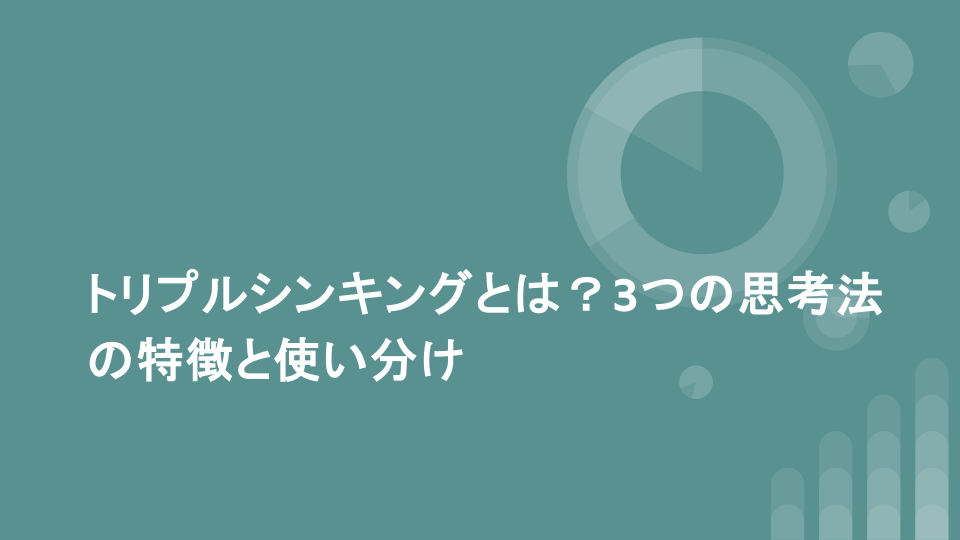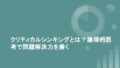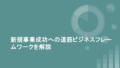- この記事の要旨 -
- トリプルシンキングとは、ロジカルシンキング・クリティカルシンキング・ラテラルシンキングの3つの思考法を状況に応じて使い分けるアプローチで、問題解決や意思決定の質を高めます。
- 本記事では、各思考法の特徴と具体的な活用場面、場面ごとの使い分け判断基準、そして実務で役立つトレーニング方法を解説します。
- 3つの視点を身につけることで、複雑なビジネス課題にも柔軟に対応できる思考力が養われ、会議での発言やプロジェクト推進で成果を出しやすくなります。
トリプルシンキングとは
トリプルシンキングとは、ロジカルシンキング・クリティカルシンキング・ラテラルシンキングの3つの思考法を組み合わせて活用するアプローチです。1つの思考法だけに頼らず、課題の性質や状況に応じて3つの視点を切り替えることで、問題解決や意思決定の精度を高められます。
トリプルシンキングの定義
ビジネスの現場では、数字で裏付けられた論理的な説明を求められる場面もあれば、既存の前提を疑って別のアプローチを検討すべき場面もあります。トリプルシンキングは、こうした多様な局面に対応するために生まれた考え方といえます。
ロジカルシンキングは情報を整理し筋道を立てて結論を導く思考法、クリティカルシンキングは前提や根拠を吟味して判断の妥当性を検証する思考法、ラテラルシンキングは既存の枠組みを離れて新しい発想を生み出す思考法です。これら3つはそれぞれ得意領域が異なり、単独で使うよりも組み合わせることで相乗効果が生まれます。
3つの思考法を組み合わせる意義
実は、多くのビジネスパーソンは無意識のうちに特定の思考パターンに偏りがちです。論理的に整理することは得意でも、そもそもの前提を疑う視点が抜け落ちていたり、斬新なアイデアを出すのは得意でも根拠が弱かったりするケースがあります。
トリプルシンキングを意識すると、自分の思考の癖を客観視できるようになります。「今は論理で詰めているけれど、前提自体は正しいのか」「アイデアは出たけれど、本当に実現可能か」といったメタ認知が働くようになる点がポイントです。
トリプルシンキングを活用したビジネスケース
ここでは、企画部門で新規サービスの検討を担当する鈴木さん(30代・主任)の事例を通じて、トリプルシンキングの活用イメージを紹介します。
鈴木さんのチームは、既存顧客向けのサブスクリプションサービスの契約更新率が低下しているという事実に直面しました。まずロジカルシンキングを用いて、解約理由のデータを整理し、「価格」「機能不足」「サポート対応」の3つに分類。次にクリティカルシンキングで「価格が高い」という顧客の声を検証したところ、競合と比較して実際には価格差がほとんどないことが判明しました。
ここがポイントです。「価格が高い」という表面的な声をそのまま受け取らず、本当の課題は「価格に見合う価値を感じられていない」ことだと仮説を立て直しました。そこでラテラルシンキングを活用し、「更新時に新機能の体験セッションを提供する」というアイデアを創出。従来の「値引き」とは異なるアプローチで、結果的に更新率の改善につながりました。
※本事例はトリプルシンキングの活用イメージを示すための想定シナリオです。
ロジカルシンキングの特徴と活用法
情報を体系的に整理し、根拠と結論のつながりを明確にする。これがロジカルシンキング(論理的思考)の本質です。複雑な情報を構造化して相手に伝える場面や、意思決定の根拠を示す場面で活きます。
ロジカルシンキングの基本的な考え方
「漏れなく、重複なく」情報を分類する。これがMECE(ミーシー:Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)の原則であり、論理的思考の土台となります。
たとえば「売上を上げる方法」を考える場合、「新規顧客を増やす」と「既存顧客の単価を上げる」に分けると、検討すべき領域が明確になります。ロジックツリーを使えば、大きなテーマを枝分かれさせながら具体的な施策レベルまで落とし込めます。
ロジカルシンキングが力を発揮する場面
報告資料の作成では、結論を先に述べ、その根拠を順序立てて説明する構成が求められます。この場面こそロジカルシンキングの強みが活きるところです。
会議での提案においても同様です。「なぜその施策を推奨するのか」を、データや事実を積み上げて説明できると、合意形成がスムーズに進みます。また、プロジェクトの計画策定時にタスクを分解して優先順位をつける作業にも、論理的な整理力が欠かせません。
ロジカルシンキングを実践するコツ
「結論→理由→具体例」の順で話す習慣をつけると、論理的な伝え方が身につきます。資料作成時には、各スライドの冒頭にメッセージを1文で書き出し、そのメッセージを裏付けるデータを配置する構成を意識してみてください。
見落としがちですが、論理が通っていても前提が間違っていれば結論は誤ります。ロジカルシンキングだけでは限界があるため、クリティカルシンキングとの併用が大切になります。
クリティカルシンキングの特徴と活用法
情報や主張を鵜呑みにせず、根拠や前提を吟味して判断する。それがクリティカルシンキング(批判的思考)の考え方です。意思決定の質を高め、リスクを事前に察知するうえで欠かせない視点となります。
クリティカルシンキングの基本的な考え方
「提示された情報の出典は信頼できるか」「データの解釈に偏りはないか」「他の可能性は検討されているか」。こうした観点で情報を評価することが、クリティカルシンキングの核心です。
仮説思考と組み合わせると効果的です。「おそらくこうだろう」という仮説を立て、その仮説が正しいかどうかを検証するためにデータを集める。このプロセスを回すことで、思い込みに基づく判断を防げます。
クリティカルシンキングが力を発揮する場面
正直なところ、ビジネスの現場では「前任者がそうしていたから」「業界の常識だから」という理由で続いている慣行が少なくありません。クリティカルシンキングは、こうした既存の前提を疑い、本当に最適なやり方なのかを検証する際に役立ちます。
リスク評価の場面でも有用です。新規プロジェクトの提案を受けたとき、成功シナリオだけでなく「何が起きたら失敗するか」を問うことで、見落としていたリスクに気づけます。
クリティカルシンキングを実践するコツ
「反対意見を自分で考える」習慣が身につくと、批判的思考力が養われます。提案資料を作成したら、自分がその提案に反対する立場だったらどう指摘するかを想像してみてください。
ここが落とし穴で、クリティカルシンキングが「否定のための否定」になると、議論が前に進まなくなります。目的は建設的な検証であり、あら探しではない点を忘れないことが大切です。
ラテラルシンキングの特徴と活用法
既存の枠組みや常識を離れて、新しいアイデアや解決策を生み出す。それがラテラルシンキング(水平思考)です。イノベーションや差別化戦略を考える場面で威力を発揮します。
ラテラルシンキングの基本的な考え方
ラテラルシンキングは、マルタ出身の心理学者エドワード・デ・ボーノが提唱した概念です。論理的に積み上げる「垂直思考」に対し、横方向に発想を広げる「水平思考」という対比で説明されます。
ゼロベース思考もラテラルシンキングの一形態といえます。「もし予算の制約がなかったら」「もし今日この事業を始めるとしたら」といった仮定を置くことで、固定観念から解放された発想が生まれやすくなります。
ラテラルシンキングが力を発揮する場面
ブレインストーミングや企画会議で「もっと斬新なアイデアが欲しい」と言われたとき、ラテラルシンキングの出番です。競合と同じ土俵で戦うのではなく、まったく異なる切り口を見つけることで差別化につながります。
マーケティング部門での商品コンセプト開発や、エンジニアリングチームでの技術課題の解決など、業界を問わず新しい視点が求められる場面で活用できます。
ラテラルシンキングを実践するコツ
「逆転の発想」を意識的に試すのが一つの方法です。「コストを下げる」ではなく「コストをかけることで得られる価値は何か」と問いを逆にすると、思いがけないアイデアが出てくることがあります。
大切なのは、出てきたアイデアをすぐに評価しないことです。「それは現実的じゃない」と即座に否定すると、発想の広がりが止まってしまいます。アイデア出しと評価のフェーズを分けることを心がけてみてください。
場面別・3つの思考法の使い分け方
トリプルシンキングを実務で活かすには、どの場面でどの思考法を優先すべきか判断できることが鍵です。問題の性質を見極め、適切な思考法を選択するための基準を整理します。
問題の性質による判断基準
課題が「情報の整理・構造化」を必要としているなら、ロジカルシンキングを優先します。たとえば、複数の選択肢を比較して最適解を選ぶ場面、報告資料で説得力のある論拠を組み立てる場面が該当します。
課題が「前提や判断の妥当性検証」を必要としているなら、クリティカルシンキングを優先します。提案内容に違和感を覚えたとき、リスクを洗い出すとき、既存のやり方を見直すときがこれに当たります。
課題が「新しいアイデアや発想」を必要としているなら、ラテラルシンキングを優先します。現状の延長線上では解決できないとき、差別化のための切り口を探すときに選択します。
思考法を切り替えるタイミング
注目すべきは、1つの課題に対して複数の思考法を順番に使うケースが多いということです。先ほどの鈴木さんの事例のように、まず整理(ロジカル)→ 検証(クリティカル)→ 発想(ラテラル)という流れで進めると、思考の抜け漏れを防げます。
逆に、アイデア出しから始めて(ラテラル)、そのアイデアの実現可能性を検証し(クリティカル)、実行計画を構造化する(ロジカル)という順序もあります。課題の性質に応じて柔軟に組み合わせることを意識してみてください。
トリプルシンキングのトレーニング方法
トリプルシンキングを習得するには、日常業務の中で意識的に3つの思考法を使い分ける練習が欠かせません。具体的なトレーニング方法と、よくある失敗パターンを紹介します。
日常業務でできる練習法
会議の議事録を取る際に、発言内容を「事実」「意見」「仮説」に分類してみてください。これはクリティカルシンキングの基礎トレーニングになります。週に1回、15分程度から始めるのが現実的です。
ロジカルシンキングの練習には、報告メールを送る前に「結論→理由→具体例」の構成になっているか確認する習慣が役立ちます。GA4などのアクセス解析ツールでデータを見るときも、数字の背景にある因果関係を言語化する練習をするとよいでしょう。
ラテラルシンキングは、SCAMPER(スキャンパー)法を使った発想トレーニングが効果的です。既存の商品やサービスに対して「代用できないか」「組み合わせられないか」「逆にできないか」といった問いを投げかけ、アイデアを出す練習を試す価値があります。
トレーニングでよくある失敗
トリプルシンキングのトレーニングでよくある失敗は、完璧を求めすぎる、知識偏重になる、成果を急ぎすぎるの3パターンです。
完璧を求めすぎると、思考法を「正しく」使えているか気になりすぎて、肝心の課題解決が進みません。まずは「今日はクリティカルシンキングを意識しよう」と1つに絞って実践するのが現実的です。
知識偏重になるパターンも見落としがちです。フレームワークの名前を覚えるだけでは思考力は身につきません。実際の業務で使ってみて、うまくいった点・いかなかった点を振り返ることで定着します。
よくある質問(FAQ)
ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの違いは?
ロジカルシンキングは情報を整理して論理的に結論を導く思考法、クリティカルシンキングは前提や根拠の妥当性を検証する思考法です。
両者は補完関係にあります。ロジカルシンキングで組み立てた論理が正しいかどうかを、クリティカルシンキングでチェックするという使い方が実務では多く見られます。
たとえば提案資料を作成する際、まずロジカルシンキングで構成を整え、次にクリティカルシンキングで「この根拠は十分か」「反論されそうな点はないか」を確認するという流れを意識してみてください。
ラテラルシンキングを鍛える方法は?
日常的に「別の方法はないか」と問いかける習慣をつけることが、ラテラルシンキングを鍛える第一歩です。
異業種の成功事例を調べて「自社に応用できないか」と考える練習が効果的です。たとえば、飲食業界のサブスクリプションモデルをBtoB事業に転用できないかといった発想トレーニングを試してみてください。
また、あえて「制約を外す」仮定を置くのも有効です。「予算が無制限だったら」「時間が半分しかなかったら」といった極端な条件を設定すると、固定観念から離れた発想が出やすくなります。
トリプルシンキングはどの場面で使うべき?
トリプルシンキングは複雑な課題に直面したとき、1つの思考法だけでは解決策が見つからないときに特に有効です。
具体的には、新規事業の企画、既存業務の改善提案、リスクを伴う意思決定、チームでの合意形成が求められる会議などが該当します。
日常のシンプルなタスクにまで3つの思考法を意識する必要はありません。「この課題は複雑だ」と感じたときに、どの思考法が不足しているかを振り返る習慣をつけることを心がけてみてください。
思考法を身につけるのにどのくらい時間がかかる?
基本的な理解は数時間の学習で可能ですが、実務で自然に使いこなせるようになるには3〜6か月程度の継続的な実践が目安です。
最初の1か月は1つの思考法に集中し、その後2〜3か月目で別の思考法を追加、4か月目以降で組み合わせを意識するというステップを踏むと、無理なく習得できます。
社内研修やオンラインセミナーを活用して基礎を学び、日常業務で実践するサイクルを回すことで定着が早まります。
トリプルシンキングとデザイン思考の関係は?
トリプルシンキングとデザイン思考は補完的な関係にあり、併用することで問題解決の幅が広がります。
デザイン思考は「ユーザー視点での課題発見と解決策の創出」に強みがあり、共感・定義・発想・試作・検証のプロセスを重視します。トリプルシンキングは各プロセスの「思考の質」を高める役割を担います。
たとえば、デザイン思考の「発想」フェーズではラテラルシンキングが、「定義」フェーズではクリティカルシンキングが、「検証」フェーズではロジカルシンキングがそれぞれ活きます。
3つの思考法のうちどれから始めるべき?
まずロジカルシンキングから始めることで、思考を整理する土台が身につきます。
ロジカルシンキングは他の2つの思考法を活かすための基盤となります。情報を構造化できないと、クリティカルシンキングで検証すべきポイントを特定しにくく、ラテラルシンキングで出たアイデアを整理・説明するのも難しくなります。
ただし、すでに論理的な説明が得意な方は、自分の弱点を補う思考法から始めるのも一案です。
まとめ
トリプルシンキングで成果を出すポイントは、鈴木さんの事例が示すように、まずロジカルシンキングで情報を整理し、クリティカルシンキングで前提を検証し、ラテラルシンキングで新たな切り口を見つけるという流れを意識することにあります。
最初の1か月は1つの思考法に絞り、週に1回15分程度の振り返り時間を設けてみてください。会議の発言や報告資料の作成時に「今日はどの思考法を意識したか」を記録するだけでも、自分の思考パターンが見えてきます。
小さな実践を積み重ねることで、複雑なビジネス課題への対応力が着実に高まり、意思決定や提案の質も向上していきます。