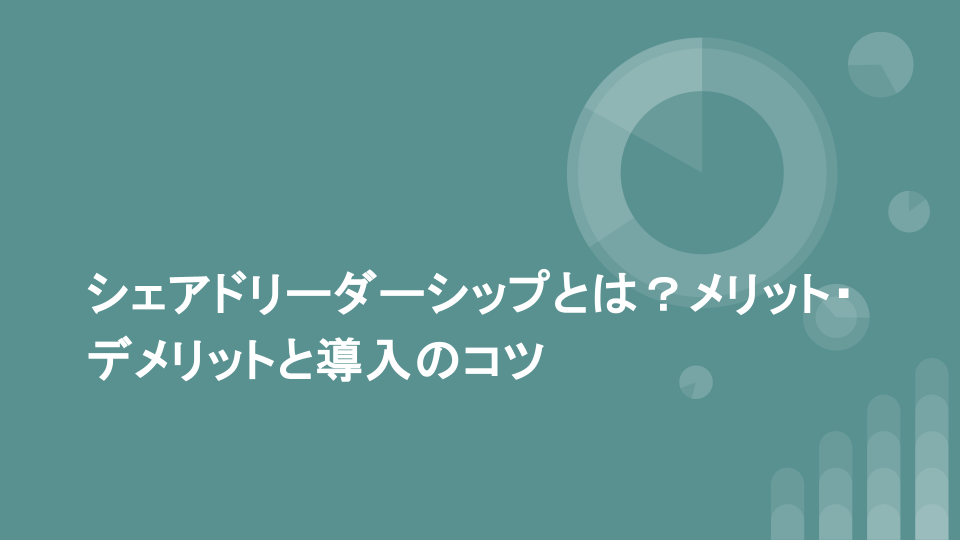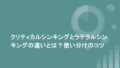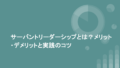ーこの記事で分かることー
- シェアドリーダーシップの定義と従来型との違いを理解できるようになる
- 導入のメリット・デメリットを踏まえて自社への適用可否を判断できるようになる
- 具体的な導入ステップと成功のポイントを把握できるようになる
シェアドリーダーシップとは|基本概念と注目される背景
組織やチームの成果を高めるうえで、リーダーシップのあり方は常に議論の的となってきた。近年、一人のリーダーに依存しない新たな形態として「シェアドリーダーシップ」への関心が高まっている。
ここでは、この概念の定義と特徴、従来型との違い、そして注目を集める背景について整理する。
シェアドリーダーシップの定義と特徴
状況に応じてリーダー役が入れ替わり、メンバー全員が影響力を発揮する。この動的なリーダーシップ形態がシェアドリーダーシップである。
立教大学経営学部の石川淳教授は、シェアドリーダーシップを「特定の個人ではなく、チームメンバー間で共有されるリーダーシップ」と説明している。固定的な役職に縛られず、場面ごとに最適な人物がリーダーシップを発揮する点が特徴だ。
たとえば、技術的な課題ではエンジニアが主導し、顧客折衝の場面では営業担当がチームを牽引する。このように、専門性や状況に応じた役割の流動性がシェアドリーダーシップの本質である。
従来型リーダーシップとの違い
一人の上司が指示を出し、部下が従う。この垂直型の構造と対極にあるのがシェアドリーダーシップである。
従来の垂直型リーダーシップでは、意思決定の権限が特定の管理職に集中する。トップダウンで方針が降りてくるため、指示系統は明確だが、現場の知見が活かされにくい。
一方、シェアドリーダーシップでは権限が分散され、水平的な関係性のなかで意思決定が行われる。階層にとらわれず、最も適任な人物がその場面のリーダー役を担う。ただし、最終責任者が不在になるわけではない点は押さえておきたい。
| 比較項目 | 従来型(垂直型) | シェアドリーダーシップ |
| 権限の所在 | 特定のリーダーに集中 | メンバー間で分散・共有 |
| 意思決定 | トップダウン | 状況に応じて流動 |
| メンバーの役割 | フォロワーとして従う | 場面ごとにリーダー役を担う |
| 強みの活かし方 | リーダーの判断に依存 | 各自の専門性を発揮 |
VUCA時代に注目が集まる理由
なぜ今、シェアドリーダーシップが求められるのか。答えは、ビジネス環境の不確実性と複雑性の高まりにある。
VUCA(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)と呼ばれる変化の激しい時代において、一人のリーダーがすべてを把握し、最適な判断を下し続けることは困難だ。市場の変化、技術革新、顧客ニーズの多様化に対応するには、現場の多様な知見を素早く意思決定に反映させる必要がある。
リモートワークやハイブリッドワークの普及も追い風となっている。物理的に離れた環境では、上司が逐一指示を出すスタイルは機能しにくい。メンバーそれぞれが自律的に判断し、協働する体制が欠かせない状況だ。
シェアドリーダーシップのメリット
シェアドリーダーシップを導入することで、組織やチームにはどのような変化が生まれるのか。ここでは主なメリットを3つの観点から解説する。
チーム全体のエンゲージメント向上
メンバー一人ひとりが当事者意識を持てる点がシェアドリーダーシップの優位性である。
従来型の組織では、「上が決めたことに従う」という受動的な姿勢が生まれやすい。しかし、自らがリーダーシップを発揮する場面があれば、仕事への関与度は自然と高まる。
オーナーシップが芽生えることで、モチベーションの向上にもつながる。「自分の意見が組織の意思決定に影響を与える」という実感は、帰属意識を強め、離職率の低下にも寄与するケースがある。
意思決定の質とスピードの両立
現場の専門知識を即座に活かせる状況を生み出すのがシェアドリーダーシップである。
垂直型の組織では、現場で課題が発生しても、上長への報告・承認を経なければ対応できない。この時間的ロスが、ビジネス機会の逸失につながることも少なくない。
シェアドリーダーシップでは、その領域に最も詳しいメンバーが主導権を握る。集合知を活かした多角的な検討と、迅速な判断を両立できる点が強みだ。
イノベーション創出の促進
多様な視点がぶつかり、新たな発想が生まれる。この創発的な環境をシェアドリーダーシップは後押しする。
一人のリーダーの視点に依存すると、アイデアの幅は限定される。しかし、異なる専門性や経験を持つメンバーが対等に意見を交わせば、既存の枠にとらわれない発想が生まれやすい。
心理的安全性が確保されたチームでは、失敗を恐れずに新しい挑戦ができる。この土壌がイノベーションの源泉となる。
シェアドリーダーシップのデメリットと課題
メリットがある一方で、シェアドリーダーシップには導入・運用上の課題も存在する。事前にリスクを把握しておくことで、失敗を回避しやすくなる。
責任の所在が曖昧になるリスク
誰が最終判断を下すのか。この問いに答えられない状態がシェアドリーダーシップの落とし穴である。
全員がリーダーシップを発揮するといっても、最終的な責任者が不在では組織は機能しない。問題が発生した際に「誰の判断だったのか」が不明確だと、対応が遅れ、信頼関係にも亀裂が入る。
導入にあたっては、「リーダーシップの共有」と「責任の明確化」を両立させる仕組みが不可欠だ。
導入初期の混乱と調整コスト
会議が長引き、結論が出ない。導入初期にはこうした混乱が起きやすい。
垂直型に慣れたメンバーにとって、「誰が決めるのか」が曖昧な状態はストレスとなる。合意形成に時間がかかり、かえって生産性が低下するケースも珍しくない。
コミュニケーションコストの増加も課題だ。情報共有の仕組みが整っていなければ、認識のズレが頻発し、調整に多くの時間を割かれることになる。
組織文化との不適合
トップダウン文化が根強い組織では、シェアドリーダーシップが機能しにくい状況を招く。
上下関係を重視する企業風土のなかで、若手が上司に意見することは心理的ハードルが高い。「自分が前に出ると生意気だと思われる」という懸念が、主体的な行動を阻害する。
組織全体の価値観や制度設計を見直さなければ、シェアドリーダーシップは形骸化するリスクがある。
シェアドリーダーシップ導入の具体的ステップ
シェアドリーダーシップを実践に移すには、段階的なアプローチが欠かせない。ここでは、導入から定着までの流れを3つのステップで整理する。
現状診断と導入可否の判断
自組織の状態を客観視することが、導入成功への第一歩となる。
まず確認すべきは、現在のチーム状況だ。メンバー間の信頼関係は築けているか、心理的安全性は担保されているか、各メンバーは自律的に動けるスキルを持っているか。これらの要素が欠けていると、導入は時期尚早となる。
エンゲージメントサーベイや360度評価を活用し、定量的にチームの状態を把握することを推奨する。
役割設計とルールの明文化
曖昧さを排除し、各メンバーの貢献領域を明確にするのがこのステップである。
「誰が、どの場面で、どの範囲の権限を持つのか」をルールとして文書化する。たとえば、技術選定はエンジニアリーダー、顧客対応は営業担当、予算管理はプロジェクトマネージャーというように、専門領域ごとの役割分担を設定する。
あわせて、意思決定のプロセスも定めておく。どの範囲は各自の判断で進めてよいのか、どの段階でチーム全体の合意が必要かを明確にすることで、混乱を防げる。
段階的な権限委譲と振り返り
いきなり全権限を渡すべきか。答えは否である。
導入初期は小さな範囲から始め、徐々に拡大していくアプローチが現実的だ。特定のプロジェクトや業務領域で試験的に導入し、課題を洗い出しながら改善を重ねる。
定期的な振り返りも欠かせない。うまく機能している点と改善が必要な点をチームで共有し、ルールを柔軟にアップデートしていく姿勢が定着への鍵となる。
シェアドリーダーシップの成功を左右する要因
導入しただけでは成果は出ない。シェアドリーダーシップが機能するためには、いくつかの条件が整っている必要がある。
心理的安全性の確保
心理的安全性とは、発言や挑戦がリスクなく行える状態を指す。ハーバード・ビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念である。
シェアドリーダーシップでは、メンバーが自らの意見を述べ、主体的に行動することが求められる。しかし、「間違ったことを言ったら評価が下がる」「失敗したら責められる」という不安があれば、誰も前に出ようとしない。
管理職は、メンバーの発言を否定せず受け止める姿勢を見せることで、安心して意見を言える雰囲気をつくる必要がある。
メンバーのスキルと当事者意識
各メンバーが専門性を発揮できる状態が、シェアドリーダーシップを機能させる土台となる。
リーダーシップを発揮するには、その領域における一定のスキルや知識が前提となる。加えて、「自分がチームに貢献する」という当事者意識がなければ、権限を渡されても活用できない。
人材育成の観点から、リーダーシップ開発の研修やコーチングを取り入れることも検討に値する。全員がリーダーとしてのマインドセットを持てるよう、継続的な働きかけが欠かせない。
経営層・管理職の支援体制
現場に任せたはずが、気づけば口出しをしている。この矛盾を防ぐ仕組みが欠かせない。
シェアドリーダーシップを掲げながら、経営層や管理職が細かく指示を出せば、メンバーは萎縮する。「任せる」と言いながら結局は介入するパターンは、信頼関係を損なう原因となる。
管理職の役割は、サポート役への転換だ。メンバーが力を発揮できる環境を整え、困ったときに相談できる存在として支援する。サーバントリーダーシップの考え方が参考になる。
ビジネスケースで見るシェアドリーダーシップの実践
理論を理解しても、実際にどう機能するのかイメージしにくい面がある。ここでは、2つの想定シナリオをもとに、シェアドリーダーシップの活用イメージを示す。
IT企業のアジャイル開発チーム
スプリントごとにリーダー役が交代する。あるIT企業が採用したのはこの方式である。
状況設定 従業員300名規模のIT企業で、新規プロダクト開発チームが発足。6名のエンジニアで構成され、アジャイル開発手法を採用している。
仮説生成 チームは「特定のリーダーに依存せず、各スプリントで最も知見のあるメンバーがリードすれば、意思決定の質が上がる」と仮説を立てた。技術選定はバックエンド担当、UI設計はフロントエンド担当が主導する体制を構想した。
評価 2週間のスプリント終了後、振り返りミーティングを実施。各メンバーがリーダー役を経験したことで、チーム全体の視点が広がったと評価された。一方、初期は調整に時間がかかる場面もあった。
選択と実行 調整コストを下げるため、Slackでの情報共有ルールを整備。判断基準を文書化し、迷ったときの相談フローを明確にした。
結果 半年後、メンバーのエンゲージメントスコアが向上し、プロダクトリリースも当初計画通りに達成できた。
※本事例はシェアドリーダーシップの活用イメージを示すための想定シナリオです。
製造業の品質改善プロジェクト
現場作業者の知見を最大限に引き出す体制を築いたのがこの事例である。
状況設定 従業員500名規模の製造業で、品質不良率の改善が経営課題に。従来は品質管理部門が主導していたが、現場の声が反映されにくい状況が続いていた。
仮説生成 「現場作業者が品質改善の主体となれば、実効性の高い施策が生まれる」という仮説のもと、ラインごとに品質改善リーダーを輪番制で設定する案が浮上した。
評価 パイロット導入した1ラインでは、現場起点の改善提案が増加。ただし、ベテランと若手の間で意見の食い違いが生じる場面もあった。
選択と実行 対話の場としてファシリテーター役を設置。週次の改善ミーティングでは、全員が発言機会を持てるルールを導入した。
結果 1年後、対象ラインの品質不良率が改善傾向を示し、他ラインへの展開が決定された。
※本事例はシェアドリーダーシップの活用イメージを示すための想定シナリオです。
よくある質問
シェアドリーダーシップを導入すると、従来のリーダーは不要になるのか?
シェアドリーダーシップを導入しても、最終責任を担う役割は残る。従来のリーダーは「指示を出す人」から「環境を整える人」へと役割が変化する。
メンバーが力を発揮できる条件を整え、困ったときのサポート役となることが求められる。リーダー不在ではなく、リーダーシップの形が変わるという理解が正確である。
どのような組織に向いているのか?
変化の激しい環境で事業を展開する組織や、専門性の高いメンバーで構成されるチームで活きやすい。IT・クリエイティブ・研究開発などの領域が代表例だ。
一方、厳格なルール遵守が求められる業務や、緊急時に即断即決が必要な場面では、垂直型のほうが機能しやすいケースもある。自組織の特性を見極めて判断することが欠かせない。
評価制度はどのように変えるべきか?
個人の成果だけでなく、チームへの貢献度を評価項目に加えることを検討する。「他メンバーの支援」「知識共有」「協働姿勢」などを可視化する仕組みが有効だ。
360度評価やピアフィードバックを取り入れ、多面的に貢献を把握できる体制を整えることで、シェアドリーダーシップと整合した評価が可能になる。
導入にはどのくらいの期間がかかるのか?
チームの状況によるが、定着までには6か月から1年程度を見込むことが現実的である。最初の3か月は試行錯誤の期間と割り切り、小さな範囲から始めて徐々に拡大する進め方を推奨する。
短期間で成果を求めすぎると、混乱のまま頓挫するリスクがある。段階的なアプローチが成功の鍵となる。
全員がリーダーシップを発揮できない場合はどうすればよいか?
無理に全員を同じレベルに引き上げる必要はない。メンバーそれぞれの強みを活かせる場面を見つけ、小さな成功体験を積み重ねることが第一歩だ。
リーダーシップ研修やコーチングを通じた育成も有効である。時間をかけて、チーム全体のリーダーシップ力を底上げしていく姿勢が欠かせない。
まとめ
シェアドリーダーシップは、一人のリーダーに依存せず、メンバー全員が状況に応じてリーダーシップを発揮する組織形態である。VUCA時代において、現場の多様な知見を活かした意思決定を可能にする点が強みだ。
導入にあたっては、心理的安全性の確保と役割・ルールの明文化が前提条件となる。6か月から1年程度の期間を見込み、小さな範囲から段階的に拡大していくアプローチが現実的である。
まずは自チームの現状を診断し、導入可否を判断することから始める。エンゲージメントサーベイや360度評価を活用し、チームの準備状態を客観的に把握することがスタートラインとなる。